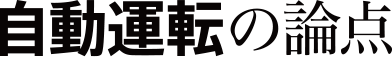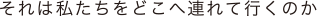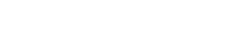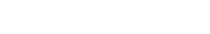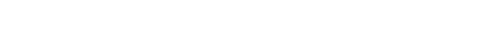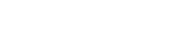モビリティで変わる社会
松浦 晋也
最新記事はこちら
自動運転は、デジタル技術の進歩によって可能になる技術のひとつに過ぎない。が、その影響は巨大であると予想されている。
自動車がドライバー抜きで自動的に走る──というだけのことで、すぐに「貨物輸送が自動化される」「ドライバーのいないタクシーが可能になる」「運転手のいないバスが運行できるようになる」などの変化を思いつく。これらの変化は次の変化を呼び込む。「自動化されたら失業する人が発生するじゃないか」「人件費が不要になるので、輸送コストが低下するのではないか」。変化はさらなる変化を誘発する。「失業者を吸収できる次の産業が必要ではないか」「輸送コストが低下するなら、より頻繁に人は移動するようになり、結果として観光が盛んになるのではないか」、さらには「では自動運転で、どのような人がどのような観光をするようになるのか。そんな観光客を集めるのはどのような観光地なのか」──このように考えていくと、運転の自動化はひとつの起点であって、そこから様々な変化がとめどもなく誘発されることが分かる。
どんな変化が誘発されるかが事前に分かれば、先手を打ってビジネスを展開できる。が、どんな変化が起きるかを知ることはおそらく不可能だろう。私たちにできることは可能な限り先入観を廃して、柔軟に考えていくことだけだ。
ひとつ、確実なのは、「私たちが予想もしなかった変化が起きる」ということである。予想に予想を重ねても、現実は予想を軽々と超えていくであろう。
では予想することそのものが無駄なのかといえば、そんなことはない。まっすぐに現実を見据えた上で考えを巡らせてていくことで、我々は思考を整理することができる。思考が整理できれば、正しい予想はできないまでも、正しい方向性を見いだすことはできるだろう。技術は常に諸刃の刃なので、自動運転がもたらす未来は、ユートピアでもディストピアでもありうる。ディストピアを回避し、ユートピアに近づくためには、正しい方向性を把握することが重要だ。正しい方向性を、可能な限り多くの人々と共有できれば、より効率的な試行錯誤が可能になる。より手早く、より確実に未来を引き寄せることができる。
この連載では、自動運転の技術的進展や、自動運転が実際にどのレベルまで実現できるか、といった技術的な興味からいったん離れて、「自動運転が実現できたとしたら、社会にどのような変化が起きると考えられるか」を考察していく。武器は想像力であり、ここまでに自分が蓄積してきた教養だ(人によっては「雑学だろ」というかもしれない。その通り、雑学こそは教養の基礎である)。
数年を経て振り返れば、当たっていることも外れていることも書いてあるということになるだろう。それで良いと思う。今はとにかく、想像力の翼を伸ばして、自動運転というテクノロジーのもたらす未来を幻視することが重要ではなかろうか。
臆せず予言者を目指そう。たとえ結果がほら吹きであっても、その行為は決して無駄ではない。