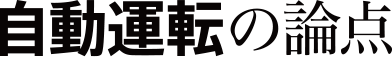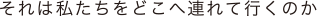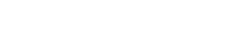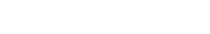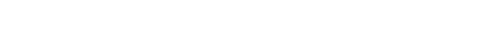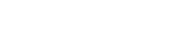技術および欧米自動車産業人事情報
坂和 敏
最新記事はこちら
現在進行中のモビリティ革命に関して、国内だけでなく海外の動向も視野に入れる必要がある。その理由として挙げられるのは、以下の3点だ。
1)自動車販売台数の約半数を中国と米国が占めている
世界全体の四輪車生産台数が9080万台なのに対して、販売台数は中国が2460万台、米国が1747万台である(合わせて4207万台=約60%)。日本の505万台は国別では第3位、ただし台数シェアでは5.5%に過ぎない。
・主要国の四輪車生産台数推移
主要国の四輪車販売台数推移
2)IT企業やシェアリング事業者の影響力の高まり
国内では「白タク」として普及が進んでいない(まださほど馴染みのない)ライドシェアリング事業者だが、同分野最大手のウーバー(Uber)が世界519都市、中国最大手のディディ・チューシン(Didi Chuxing)が中国国内約400都市でサービスを提供し、後者ではすでに1日の利用回数が1100万回に達するなど、社会的に大きな影響力を及ぼすようになっている。またこれらの事業者に公共交通機関の機能の一部を任せる実験なども米国の一部では始まっている。
一方で、既存の自動車メーカーのなかにも「移動手段(“Mobility Solutions”)の提供」を打ち出したフォードのような例も出ており、グーグルやバイドゥなどネット企業としてスタートした大手企業も、この分野の取り組みを熱心に進めている。これまでは自動車メーカーの範囲にとどまっていたテスラは、実質的にエネルギーおよび運輸(transportation)分野を活動範囲とする企業に変身しつつある。このように、従来の「業界」の区分が意味を失いつつある。

3)「解決すべき課題」の地域による違いや共通点
技術の開発や実用化などとは別に、社会による受け入れ方は国や地域によって異なる。過疎や高齢化といった社会的問題の緩和・解決の手段のひとつとして、自動運転車やシェアリングサービスに期待が集まる日本と、都市化に関わる問題の解決策(渋滞緩和や大気汚染抑制)として注目が集まる米国や中国、欧州の一部の国などとは自ずと事情が異なる。
その一方で、社会インフラの再構築や、経済的弱者への移動手段の提供といった視点から、これらの技術やサービスを活用する動きも米国などではすでに見られる。これは、日本国内の過疎地域における高齢者への移動手段提供と、相通じる問題と考えられる。