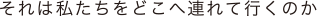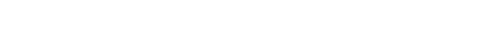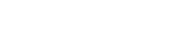アメリカの本音
長野 美穂
最新記事はこちら
長野美穂と申します。米国のカリフォルニア州に住み、記者の仕事をしています。西海岸のカリフォルニアに住む前は、ミシガン州に住んでいました。ミシガンとカリフォルニア、アメリカの自動車産業を代表するふたつの州で暮らしてハンドルを握り、自動車産業を取材してみると、同じ「クルマ」を取りまく人々がこの2カ所では、全く違う世界に住んでいることがわかります。
デトロイト自動車ショーは毎年、極寒の冬に開催されますが、まず、市内から会場のコーボー・センターに行くまでの道がボコボコです。ボコボコというのは比喩ではなく、文字通り、道に大きな穴が開いていて、これを英語でpothole(ポットホール)と呼びます。ちなみに発音は「パットホール」です。完全に凍結し、雪に覆われた道路のあちこちに大きな穴があり、うっかりそこにタイヤが落ちると、タイヤが損傷して走れなくなるという「地雷」か「落とし穴」のような危ないシロモノです。
財政破綻のデトロイトには道路修理をする資金がないため、無数のポットホールが放置されたままです。よって、デトロイト市民はこの穴を事前に察知し、よける運転術に非常に長けています。16歳のドライバーでも高齢者ドライバーでも、です。さらに、道には雪対策のために、塩が撒かれており、巨大SUVからコンパクトカーまで、全てのクルマが塩まみれの車体で走っています。
デトロイトは米国自動車産業の中心ですが、自動車の盗難数が全米でもトップクラスに多いため、自動車保険の金額が跳ね上がり、その高い保険が払えずに、クルマを所有できない人々が急増しています。カナダ国境から吹く雪混じりの強風を受けて、道路の穴に何とか落ちずに、コーボー・センターにたどり着くと、そこには、GM(ゼネラル・モーターズ)の男性幹部たちが、ずらっと揃っています。
体格のいい身体に黒スーツ、そして彼らの指には太い金の指輪がはまっています。キャデラック車の往年のイメージそのままです。彼らが小柄なCEOのメアリー・バーラ氏を取り囲むように歩くと、まるで、数十人の屈強なボディーガードたちが女王を守っているかのように見えます。
「デトロイト・セントリック」。デトロイトが世界の中心だという思考は、GMの遺伝子に埋め込まれていますが、それも、GMが破産法の適用後、税金の注入を受けて再出発したり、ウーバーやリフトなどのカーシェアリング・ビジネスの台頭で、少しずつ変容を見せています。
それに対して、ヤシの木が揺れ、サーファーたちがビーチを行き交うカリフォルニアはどうでしょうか。ロサンゼルスではポルシェやBMWなどの高級車も当たり前のように無造作に路上駐車され、405と呼ばれるフリーウェイでは、朝から夜中まで渋滞が続きます。
ロサンゼルスの405上では、交通事故があっても、転がった車体がボーボーと炎を出して燃えていても、銃の撃ち合いがあっても、ドライバーたちは、ミラーをちらっと見るだけで、減速することなく、猛スピードでその横を走り抜けていきます。事故だから減速しよう、などとブレーキペダルを踏むと、0.5秒も経たないうちに後続車からクラクションを鳴らされます。
違反切符を切られたドライバーたちが裁判所命令で通わなければならないドライビングスクールの授業では「高速道路でドライブ・バイ・シューティング(銃の撃ち合い)があったら、窓を閉め、減速しないでそのまま一気に走り抜けるのが一番」と教官が教えていました。そして、シリコンバレーにあるベンチャー企業の駐車場に行けば、エグゼクティブたちの駐車スポットでは、ピカピカのテスラ車が充電中だったりします。また、カーウオッシュのサービスが社員たちに無料で提供されていて、洗い上がったクルマが次々に出てきます。
シリコンバレーに自動運転の開発拠点を作ったGMの幹部のひとりがロサンゼルス自動車ショーでこう語っていました。「シリコンバレーのカルチャーがどんなものかを体感してほしいので、デトロイトからカリフォルニアに出張するGM社員には、AirBnBで宿を取り、ウーバーやリフトを使って移動しなさいと口を酸っぱくして伝えている」。
黒スーツに金の指輪をはめたデトロイトのGM社員たちにとって、ジーンズにTシャツでビジネスをするカリフォルニア文化は、異文化です。「ビッグデータ」という言葉がシリコンバレーで使い古され、もうbuzzらなくなった頃、この言葉はデトロイト自動車ショーで頻繁に使われるようになりました。
デトロイトとカリフォルニアにはフォッサマグナのような大きな溝が存在しているわけですが、この2カ所で、いま、同時に自動運転車の開発が行われています。しかし、普通の米国市民にとっては、自動運転の実現化はまだまだ先の未来の話の感が強いです。ひとりが一台クルマを所有するのが当たり前、という文化で育ったアメリカ市民たちにとっては、ウーバーやリフトなどのカーシェアリング文化が流行ろうと、それはあくまで都市部での現象であり、田舎や郊外では全く別の現実が広がっています。

この夏、北ミシガンのアメリカ人の友人宅を訪ねた時、友人の高校生の息子(15歳)がこう言いました。「僕、16歳になって免許が取れたら、ジープが欲しいな」。「ジープ?いくらするかわかってんの?高いのよ!」と母親である友人が言います。「でも、カッコいいし、いろいろ運ぶのに便利だし、秋の狩猟シーズンには森で重宝するし、女の子にもウケが良さそうだし」。ちなみに、ジープはフィアット・クライスラーの製品です。
バスや電車などの公共交通機関が存在しない北ミシガンに住む16歳の彼には、自分のクルマを持つことは、親のコントロール下から脱却して、自由に行きたいところに、行きたい人と行けることを意味します。シャイなこの少年は、陸上部でクロスカントリーに熱中していますが、同じ部の気になる女の子をデートに誘うのも、クルマがあって初めて成りたつ話です。
母親の運転するSUVで部活の練習場から試合会場まで、あらゆる場所に送迎してもらなければ成りたたない15歳の今の生活と比べたら、免許とクルマを手にする16歳の世界は、もはや異次元なのです。「まったくもう、私が16歳の時に手にした最初のクルマなんか、ものすごいボロ車だったのに、あの子、ジープなんて、何、贅沢言ってるのかしら」。そう言いながらも、地元新聞の「中古車売ります」の広告欄を見ながら、息子のために安いジープが売りに出ていないか探す友人。
多くの米国人にとって、マイカーは生活の一部であり、日常も非日常も嬉しいことも悲しいこともクルマと共に体験します。そして、自分でハンドルを握り、エンジンをかけ、どこにでも好きな所に行かれることは、アメリカ人に言わせれば「自由」の象徴でもあります。そんなクルマ大国米国で、フツーの人々にとってクルマとは何なのかを考えながら、今後、自動運転という未来のテクノロジーが彼らの生活とどう関わってくるのかも考えていけたらと思っています。
ちなみに、アメリカ人男女と必ず盛り上がれる話題は「あなたが最初に買ったクルマは何?」です。ホラーのような体験談、ちょっぴりほろ苦く甘い青春思い出話などがエンドレスで繰り広げられること必至です。ちなみに「最初に買った車は?」の質問にまず99%の確率で還ってくる答えは「a piece of junk(ボロ車)」です。これはミシガンでもカリフォルニアでも共通です。