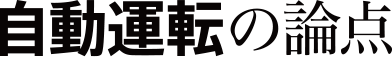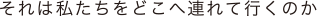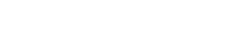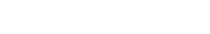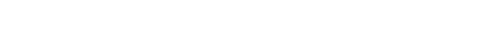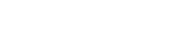海洋研究に学ぶ自動運転の意義
高井 研
最新記事はこちら
海洋研究が自動運転に提供できる論点として、2つのものが挙げられる。一つは、自律して水中を航行する自律型無人探査機(AUV:Autonomous Underwater Vehicle)について。もう一つは、生物の生存戦略としての移動についての根本的な議論だ。
移動することは生物にとってリスクであり、リスク分散でもある。移動することで個体が死ぬリスクが増えるが、種の分布が広範囲に広がることで、種全体の生残確率は上がる。ヒトには、wanderlust gene(wanderlust=旅好き、放浪癖)と呼ばれる遺伝子があることが示唆されている。未だ不確定な部分も多いが、ヒトの20%程度が持つと言われているこの遺伝子「DRD4-7R」は、人の好奇心や落ち着きの無さに関わっているとされ、これを持つ人は探究心が強いことが示唆されている。
「あの地平線(水平線)の向こうには何があるのだろう」。おそらくそのような行動原理に基づいて移動してきたヒトは、今や世界中に分布している。移動のリスクを取って探求する個体がいたからこそ、局地的な気候変動などによって絶滅することなく、繁栄することができたのだ。
前半の6章では、「生命とは何か」という問題に取り組んできた科学者からの視点で、「誰一人知らない真実」や「今ここにはない世界」を探求するために必要なものは何か考える。自動運転の技術が世界に何をもたらすのかは、現段階では何とも言い難い。しかし、日頃から現実を乗り越え、新たな可能性を生み出す力を磨いている科学者の視点から、伝えられることがあれば良い。

後半の2章では、自律型無人探査機(AUV)や、生命の移動についての研究から、自動運転の議論のための補助線を提供したい。
海洋研究開発機構(JAMSTEC)には、深海巡航探査機「うらしま」や、「じんべい」「おとひめ」「ゆめいるか」などの深海探査機がある。これらの探査機は、AUV(Autonomous Underwater Vehicle)と呼ばれ、あらかじめプログラムされたコースを、障害物を避けながら自律して航行し、与えられたミッションを行う。
JAMSTECでは、電波の届かない海中でAUVの位置を検出するために、GPS・電波通信に頼らない慣性航法装置を開発している。また、探査機と母船の間の通信や、障害物の認識のために用いる音波技術についても開発が進んでいる。
これらの知見が、自動運転に関わる読者の仕事に役立ち、知的探究心を刺激することにつながれば幸いだ。