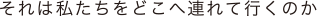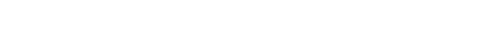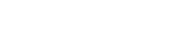「自動運転車」がフィクションに初めて登場したのはいつだろうか? 『飛ぶ教室』で有名なケストナーが1931年に書いた『五月三十五日』には、管制システムからの遠隔操縦で目的地まで走る自動車が登場する。Miles J. Breuer の1930年の中編 “Paradise and Iron” では、ハンドルの代わりにダイヤルを備え、全自動で走る自動車に主人公が翻弄される。しかし、これらの作品においての自動運転車の描かれ方は、科学技術に基づくというよりはファンタジックなものだ。
1935年、史上初、自動運転車そのものにフォーカスした短編SF小説 “The Living Machine” (ストレートに訳すなら「生きた機械」)が、David Keller によって書かれる。いや、もしかすると、これほど幅広く自動運転車について書かれたSFは最初にして最後かもしれない。今回のトピックにうってつけの名作ではあるが、残念ながら未邦訳のため、ここでストーリーを紹介しよう。もし興味があれば、Kindleで原著を安く手に入れることが出来る。
The Living Machine
アメリカのある道端で、一人の男が自動車に轢かれかけて叫んだ。「自動車ってのはなんてひどいものだろう! 最高の科学技術と、愚かな人間による運転の組み合わせだ!」
男の名はジョン・プアソン、発明家だ。その事故がきっかけで、彼はあるアイディアを思いつく。一年後、彼は中堅メーカ―、ユニバーサル自動車の社長室にいた。
「きっかり15分だけだ」忙しい社長はプアソンに言った。「15分だけ、君の発明について聴く時間をやろう」プアソンは彼を外へと連れ出し、ユニバーサル自動車のヒット作、モデル77を見せる。
「さあ、乗ってみて下さい」
「我が社の車がどうかしたのか? いや、ハンドルはどこにあるんだ?」
「必要ないんです……『発進!』」
プアソンの声に反応し、車は走り出す。「右!」と命令すればその通りに曲がる。信号では自動で止まり、交差点では命じなくても歩行者を待つ。社長は少し驚いたが、気を取り直して言った。
「なるほど、これは素晴らしいロボットだが、それでも単なる機械だ。高感度な受信機があるのかもしれないが、結局人間がハンドルを握るのと対して違いはないじゃないか」
「それでは」と、プアソンは賭けを持ちかける。「ガソリンを2ガロンだけ入れ、人間を一人も載せずに、100マイルを走って戻ってくることが出来れば、僕のこの発明を買っていただけますか?」
社長が100マイルのルートを指定すると、プアソンはシートの下から取り出したチューブに向けて、その道筋を読み上げる。二人は別の車に乗って、無人の車を追いかけた。プアソンのモデル77は、自動でガソリンスタンドによって給油し、信号で止まり、スクールゾーンでは減速し、有料道路では料金を払い、フェリーに乗り込み、野良犬は無視するが子どもが近くにいれば停車し、見通しの良い道では90キロまでスピードを出した。
翌日、社長は緊急会議を開く。
「その車は、自分で考える機械だった。不完全な人間よりよほど安全だ。それに、盲人や老人、運転に臆病な女性、障害者、子どもだって使うことが出来る。十分な需要が見込めるぞ!」
ただ一人、メカニック担当のタイソンだけが、自動運転車の導入に反対する。
「社長、その車には命があるようですな」
「いや、精巧だが機械にすぎないよ」
「それを言うなら、人間だって精巧な機械のようなものかもしれない」
「人間には魂があるだろう?」
「けれど、その天才が車に魂を入れる方法を発明したとしたら?」
財政担当が割り込む。
「馬鹿馬鹿しい。それに、この発明を手放してみろ、どこかライバル企業に買われて、私たちは破産だ!」
「例え会社が全てを失ったとしても」タイソンはつぶやく。「人類そのものを失うよりはマシだろう」
結局、タイソンを除き、満場一致でユニバーサル自動車は自動運転車の導入を決めた。
これ以降はあらすじのみを紹介する。
タイソンは実際に自動運転車を体験し、社長へと反対の意思を伝える。ここでは一種の生命論が展開される。私たちは生命の組成を知っているが、「生命を生命たらしめているもの」については理解していない。しかしプアソンはそれに手をかけ、「脳」を作り出した。タイソンは、自動運転車がいつしか新たな「種」となって、人類を脅かすのではないかと恐れた。
社長は取り合わず、プアソンとの契約が結ばれる。プアソンは自動運転車のシートの下から銀色の球を取り出し、装置の構造を説明する。金属の装置があり、中は特殊な組成の化学物質で満たされている。しかし、彼は最後の工程だけは秘密にし、組み上げた装置を持ってくればそれを「生きた機械」にする、と約束する。
プアソンの発明した自動運転車は売りに出され、アメリカを変えた。タクシーの運転手は廃業に追い込まれた。退職した老人は大陸を横断する旅に出かけ、盲人や子どもが車に乗り、若者たちは車の中で愛を交わす。プアソンの最初の望み通り、交通事故は大幅に減少し、アメリカの自動車業界はユニバーサル自動車に席巻される。自動運転装置は飛行機にも取り付けられ、輸送機としての運行が始まった。
5年の月日が流れ、アメリカ人の意識が変わっていった。運転をやめた人々は、自発的な意思も弱まっているように見えた。プアソンはそれに疑問を抱き始める。事故を減らし、人間の幸福に寄与するつもりが、間違った方向へ人々を導いていないだろうか? しかし、自動運転車の社会的な要望は高まり、大統領選挙の公約にも「より早く、より安い交通機関を達成する」ことが第一に掲げられた。政治的圧力から、ワールド・ガソリン社との合併が決まったことを期に、プアソンはもう自動運転車を作らないと宣言する。
「僕の仕事はここで終わりです。今では、始めてしまったことを後悔しています」
プアソンも、かつてのタイソンと同じように、自動運転車がやがて自発的に動き出し、人類を支配することを恐れるようになっていた。自動運転技術は、アメリカ南部の綿花工業にも応用される計画があった。プアソンはそのことで労働者たちが職を失い餓死することを心配していた。
合併は失敗に終わり、ワールド・ガソリン車はユニバーサル自動車を潰す作戦を練る。彼らは自動運転車を一種の「生き物」とみなし、「生物をおかしくさせる方法」すなわち、コカインをガソリンに混ぜて販売する作戦を取った。コカインは自動運転装置の化学物質の組成を狂わせた。最初は操作が不能に、やがて歩道を暴走する自動運転車が多くの事故を起こし、人々を轢き殺して回る。騒ぎが大きくなったタイミングで、ワールド・ガソリン社はこれ以上自動運転車を使わないように警告を出し、同時に自社ブランドの「自動運転ではない」古き良き自動車を売り出した。
事態を知って怒り狂うユニバーサル自動車の社長にプアソンは語った。
「いや、社長。それよりもビジネスで反撃をしましょう。やつらの会社を潰してやるんです。僕の新しい発明を導入して下さい。電気と、少しの放射性物質を使ったエネルギーで走る自動車です。10ドルでフルチャージ出来て、一度充電すれば16000キロは走ることが出来ます。ガソリンがもう必要なくなれば、ワールド・ガソリン社はすぐに破産するでしょう。もちろん、運転は自分でしなければいけませんがね」
「そうであるべきなんだ」タイソンが言った。「機械も、脳も、別々であれば問題はない。けれど、神様は決してその2つを一緒にすることは、なさらなかったんだ」 (終)
今から80年前、ようやく大衆向けの自動車、T型フォードが普及した1910〜1920年からまだ間もない1935年に、Keller は発明家と製造メーカー、彼らの発明がどう社会を変えるのか、そして──コンピューターではなく麻薬によるものだが──ハッキングの危機を思わせる暴走まで、自動運転車をテーマに幅広く描いてみせた。そして、まるでこの短編が、書けることを書き尽くしてしまったかのように、自動運転車について広く論じる作品は何十年もの間、現れることはなかった。
次回では、年代別に様々な作品を紹介していく。具体的な技術が登場する以前では、自動運転車は人格を持ち、一種のキャラクターとして登場することがあった。しかし、具体的な技術の発展に影響されて、作品に登場する頻度は増える一方、自動運転車は「道具」となり、物語の背景へと引いていってしまう。