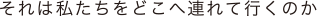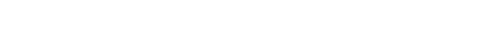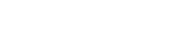クルマの自動運転が始まると、価値観も、美意識も変わると思います。エンジンからモーターへ、ガソリンから電気へ、ドライブからモバイルへと変わることで、移動への欲望の質がはっきりと変わるからです。ガソリンエンジンは「荒ぶるマシン」であり、ドライバーがこれを制御することでスピードを我がものとし、「行く」という自由を謳歌することができました。一方で、電気で動くクルマは「行く」美学ではなく「移動する」美学です。それはマシンを操る快感にではなく、「移動」を最短・最少エネルギーで実現したいという冷静な意欲に呼応します。居眠りをしている間に到着、という状況も積極的に受け入れます。また、移動のための「モバイル」は、空気のように日常に寄り添う存在であるため、最も必要であるにもかかわらず、所有欲やあこがれの対象にはならないでしょう。
今日のクルマは移動とスピードへの欲望という土壌に育った果実です。コンクリートでできた大蛇のように荒々しくうねる東京の「首都高」には、東京という都市を織りなしてきた人々の欲望が反映されています。美しい都市景観を保つよりも、戦後の復興と、先進国の仲間入りをしたという焦りが日本にはあったようです。都市における迅速な移動手段をいち早く手にしたいというのは国家の欲望でもあったのかもしれません。その欲望が1964年の東京に「首都高」というかたちで具現されたわけです。河川の上や住宅の上を跨いで敷設された道路はそうして生み出されたのです。今日、クルマが変わりはじめているということは、移動への欲望のかたちが変わりはじめているということです。
一方で、レジャービークルは、自然志向の高まりとともにさらに進化していくはずです。人為の痕跡もないような極まった自然の中に、先端テクノロジーを駆使してぽつりと存在したいという衝動は、理性に自負を持つ人間の根源的な欲望のひとつかもしれません。植民地時代の西洋人が、ことさら極まった野性的環境の中で、白いテーブルクロスと、白服の給仕係をともなって、フルコースの食事をしたがった心性も同じ動機に起因するものでしょう。電気がエネルギーとなるなら、キャンピングカーは一気に高性能・快適化していきそうです。移動ツールのみならず、情報ツールとして、さらには居住性や快適性を高めるツールとしてクルマが発展すると、人やエネルギーインフラからかけ離れた異界の自然環境は、心地よい楽園になるかもしれません。そういう場所にも、クルマの進化が生み出す新たな美意識が芽生えてくるかもしれません。